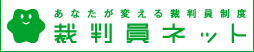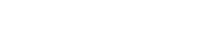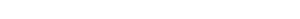第2部:裁判員制度への「想い」―若狭勝弁護士の裁判員制度に対する情熱とその原点―
第1部ではこれまでの刑事司法の問題点と、なぜ裁判員制度が出来たのかということについて、若狭弁護士の見解を伺いました。第2部では裁判員制度のスタートに合せて検事をやめ弁護士として活動を開始した若狭弁護士の「想い」とその情熱の原点について迫ります。
判決に市民が関与することの問題点
インタビュアー市民の感覚からすると、裁判所は「無茶」なことを市民に求めている感じがすることがあります。ですから、不安になってしまうんですよね。なにかすごいギャップを感じるのですが。
 若 狭死刑判決もそうなんです。あれも僕に言わせると、市民が死刑判決を言い渡すのは、僕は非常に難しいのかな、という思いがあるんですよ。つまり、裁判官が死刑判決を出すのは、それは国民の一人として支持しますけど、自分が直接目の前にいる被告人に対して、いわば「あなた死になさい」っていうことを言うわけです。そういうことは「普通の市民の心」を分かってないんじゃないかと思うんです。つまり、裁判員になった人が、その後裁判員が終わってからも、「あの人死刑になったのかどうか」という思いがずっと残る。そして「死刑になりました」と報道されるわけです。「自分があの時に、やっぱ死刑だって一票入れたから、死刑になったんだ」と思う。すると、死刑になった後もずーっと、今まで平穏に暮らしていた市民であるその裁判員は、一生、たまたま裁判員になって死刑判決に関わった。そのことで、その人の心の中にずーっと、一つのなんて言うんですかね…。「思い」が残る。ずーっと、老後まで「自分は死刑判決に関与した」という思いを抱かせるようなことは、僕はシステムとしておかしいと思う。僕自身は死刑制度は検事をやっていたっていうわけじゃないですが、やっぱり存続すべきだと思います。しかし、それを一般市民に関与させるのは、一般市民の普通の感覚からすると、私も周りの家族になんかに聞くと、とてもじゃないけどできそうもない。裁判所はそれも含めて「みんなで決めることですから大丈夫です」と説明をするわけですよね。
若 狭死刑判決もそうなんです。あれも僕に言わせると、市民が死刑判決を言い渡すのは、僕は非常に難しいのかな、という思いがあるんですよ。つまり、裁判官が死刑判決を出すのは、それは国民の一人として支持しますけど、自分が直接目の前にいる被告人に対して、いわば「あなた死になさい」っていうことを言うわけです。そういうことは「普通の市民の心」を分かってないんじゃないかと思うんです。つまり、裁判員になった人が、その後裁判員が終わってからも、「あの人死刑になったのかどうか」という思いがずっと残る。そして「死刑になりました」と報道されるわけです。「自分があの時に、やっぱ死刑だって一票入れたから、死刑になったんだ」と思う。すると、死刑になった後もずーっと、今まで平穏に暮らしていた市民であるその裁判員は、一生、たまたま裁判員になって死刑判決に関わった。そのことで、その人の心の中にずーっと、一つのなんて言うんですかね…。「思い」が残る。ずーっと、老後まで「自分は死刑判決に関与した」という思いを抱かせるようなことは、僕はシステムとしておかしいと思う。僕自身は死刑制度は検事をやっていたっていうわけじゃないですが、やっぱり存続すべきだと思います。しかし、それを一般市民に関与させるのは、一般市民の普通の感覚からすると、私も周りの家族になんかに聞くと、とてもじゃないけどできそうもない。裁判所はそれも含めて「みんなで決めることですから大丈夫です」と説明をするわけですよね。
インタビュアーそうなんです。「6人で決めることですから負担は6分の1です」と説明されますが、でもその6分の1というのはケーキのように分けられる話ではなくて、一票を入れて「合意した」という事実のほうが重いわけです。それをそういうふうにスパッと説明されると、市民としては「何を言ってんだろう」と思ってしまいます。
若 狭問題点としてもっと言うと、例えば裁判員の1人が「無罪だ」と思っている人がいるとします。ところが、多数決をとったら有罪になったと。有罪になったとしたら、今度は「死刑か無期懲役か」を「無罪だ」と思っていた人も選択しなきゃいけない。これってすごい2重人格になるわけです。それはかなり大変な話だと思います。
インタビュアーちなみに、その場合「いや、私は無罪と主張しているから、量刑の評議には参加しません」と表明することってできるんですか?
若 狭今の制度だとできないですね。これは、現行システムの問題なんです。裁判官は3人のうち2人が「有罪だ」と言い、1人の裁判官が「無罪だ」と言っても、2人で有罪になるから、今度は量刑の話になるわけです。その場合この「無罪だ」と言っていた人も量刑に加わるので、制度としては同じなんです。ただし、こっちは裁判官で「プロ」ですから。でも一般市民の感覚だと、無罪だと思っていたのが多数決で有罪になった。「じゃあ君、手のひらを返して死刑か無期懲役かどっちか言いなさい」と強要されることになるわけですよね。
裁判員裁判の「致命傷」は「冤罪」
若 狭ま、色んな問題点はあるのですが、ただ私自身は裁判員制度は、冒頭(第1部)で申し述べたように、やりようによってはかなり意義のあるいい制度だと思っています。ですから、何とかこれを維持存続させたいという思いが強いですよね。そのためには(見直しまでの)3年間の間に、情報をオープンにするなり、問題点をいっぱい浮き彫りにするということが、とにかく大事だと思っています。私自身、検事を26年間やってきました。このまま行けば近々に「検事正」という、要するに各都道府県のトップの検事として「1、2年以内にはなるんじゃなかろうか」と言われたのですが…。それをこの3月31日に退官したというのは、まさしく裁判員裁判を、弁護士の立場で、維持存続発展をさせたいと。弁護士だから、この状況の下では、そういう形での維持・存続が可能になるというふうに信じてしまったというか、信じて止まなかったのです。どういうことかと言いますとね…。裁判員裁判で、「致命傷」になることって何だと思います?
インタビュアーなんでしょう。ちょっと想像がつかないのですが…。
若 狭それはですね、要するに裁判員裁判で、「冤罪」の判決を出すっていうことですよ。
なぜ検事を辞めたのか―冤罪を防ぐ弁護士を目指して
 若 狭これはですね。今まで足利事件なんかにしても、「警察とか検察ないし裁判所が悪かった」ということで、それでとりあえずは終わっていたわけです。もちろん悪いのですけれど、しかし今度は、一般市民や裁判員が冤罪を起こしてしまったとなると、「一般市民を冤罪に関与させてしまう」そういう制度自体問題ではないかと。「そんなもんやっぱり駄目だ」と。いうことになってしまって、いわば「致命傷」みたいな形になるのです。
若 狭これはですね。今まで足利事件なんかにしても、「警察とか検察ないし裁判所が悪かった」ということで、それでとりあえずは終わっていたわけです。もちろん悪いのですけれど、しかし今度は、一般市民や裁判員が冤罪を起こしてしまったとなると、「一般市民を冤罪に関与させてしまう」そういう制度自体問題ではないかと。「そんなもんやっぱり駄目だ」と。いうことになってしまって、いわば「致命傷」みたいな形になるのです。
だから、そういう意味において、私はそれを防げるのは誰かと言った場合に、弁護士しかいないと思うのです。「しかない」と言うときっと語弊がありますが、弁護士が非常に大きな役割を演じると思っているのです。というのは、要するに、検事のほうが起訴しているわけですから、有罪だと思っているわけです。そのまま突き進みますよね。そこで、一般市民である裁判員に「この事件はこういう点で問題点がありますよ」と、問題提起ができるのは、そういう意味では弁護士しかいないのです。問題提起という面ではね。そこで、その「問題提起」をすることができるだけの、経験とか意欲とか情熱とか、そういった弁護士が必要になるわけです。私はそういう役割を演じたいと。そういうふうに思って弁護士になり、冤罪などが発生しないように、それによって裁判員裁判が致命傷を負うことがないように、弁護士としてとにかく邁進したいということで検事を辞めた次第です。
冤罪が発生する原因は2つある
インタビュアーなるほど。では敢えてお伺いするのですが、検察官という立場でも、たとえば証拠を提示する際に、当然冤罪が起こらないように皆さんやっていらっしゃる、と思うのですけれども。ちょっと踏み込んだ質問になってしまうのですが、その立場では「冤罪は防げない」という認識なのでしょうか?
若 狭おそらく、冤罪が発生する原因というのは大きく分けて2つあると思うんですよ。一つは、(取調べ段階で)要するにやはり取り調べ過程において、無理な取調べがなされて、虚偽の自白を誘発したといった場合がまず冤罪になる可能性が一つあるわけですね。もう一つは、(訴訟段階で)常識的に見たら有罪だけれども、実は違うんだと。だから、よく言う「事実は小説より奇なり」とかもしくは「偶然が偶然を呼ぶ」とかそういったところに、実は冤罪の可能性っていうのが残っているのですよ。裁判員裁判は短期間でやります。前は一年間くらいかけて、裁判官が色んなところにある問題点を突っ込んだりして、無罪にするってことが可能だったと思うのです。しかし、この4、5日くらいで、しかも「常識で判断してくださいね」っていうわけですよね。「みなさん、市民の常識で判断してください」というからには、検事だって常識で判断しているのです。そうすると、ほとんど変わらなくなってしまうのです。でも、実際は「常識」というものには「危険性」や「ごまかし」があります。もしくは「常識も変わっていく」というようなことがあるとすると、「冤罪の可能性」は、むしろ「現状の裁判よりも少なくなる」ということは、僕は「ない」と思うのです。
もう一方の「取調べにおける虚偽の自白」といったことは、裁判員裁判を入れることによって今よりは減ると思います。だから、こういう形で分類して考えないといけません。それを一緒にして、「冤罪が増える」とか「減る」とか言うのは多分僕は当たってないと思うんですよ。
司法修習生時代のある体験…
インタビュアーこれまで検事をされてこられて、今年から弁護士という立場を選んだということで、お伺いします。先生の検事時代やこれまでの法律家の立場で、お話できる範囲でかまわないのですが、「失敗してしまった経験」あるいは「苦い思い出」のようなものがおありなのでしょうか?
若 狭失敗したこと…。失敗したっていうよりも、僕は「冤罪、冤罪」って騒いでいますけど、それは実は司法修習生のときに、そもそも検事になったのは「冤罪を防げるのは検事だ」と。「直接的・直裁的に冤罪を防げるのは検事だ」という思いを抱いたんですよ。それはなぜかって言うとですね、ある体験があるんですけれど…。
司法修習生っていうのは、実務修習といって検察庁4ヶ月、弁護士4ヶ月、裁判官4ヶ月、当時はね。三箇所回っていたのです。司法修習ということで。それで、私は修習生として、とりあえず検察庁の修習に行きましたら、ある強制わいせつ事件の否認事件の論告だったのです。それで、その時検事の横に座って論告を聞いていて、「あー、否認しているんだな」と思って聴いていたら、その後、弁護修習に行きましたら、その事件の担当弁護士の所での修習だったのです。さらにいうと、裁判修習に行きましたらその事件の担当裁判官のもとでの修習だったのです。つまり、全部を見たんですね。
その事件は最高裁まで行って有罪でした。でもね、私はこれ今でも「冤罪」だと思っています。どうしてかって言うと、この被告人は坊主頭で、目がくりんとしていてかなり特徴的な顔していたのです。一度見たらほとんど印象に残るような顔つきなのですけどね。ところが、弁護修習をやっている時に弁護士が色々興信所を使って調査しましたら、きわめて近い所に、ほとんど同じような格好の頭が坊主で目がくりんとしている人が住んでいるんですよ。別人が。で、その人は、実は強制わいせつだかの前歴があるらしいんです。結局その人を隠しカメラで撮って写真を法廷に持ってきて、証人をもう一度高等裁判所に呼んで、もう一度審理をし直したのです。でも、まあ一度一審で証人が皆「被告人に間違いない」って言ってしまっている関係などもあり…。写真だととにかく初めて見ると「どっちだか区別がつかないほど」なのです、実際問題ね。でも一応(犯人は)「被告人だ」ということ証言を再度したものだから、有罪になったのです。
修習生時代のことが全て原点にある
 若 狭目撃供述っていうのは「いい加減」なんですよ。人間の供述って言うのは本当に「いい加減」なんですよ。そこから出発しないといけないです。逃げていく最中の後姿とか横顔をね、チラって見ただけで、その後「全部間違いない」って話しになるわけです。しかしそんなものってのはね、逃げる時には、要するに「強制わいせつをした犯人だ」と分かっていればもっとしっかり印象に残りますが、公園の中をバーって走っていく姿だけですから、「なんか用事があって走っているんだろう」っていうふうに思えば記憶にだってそんなに残るわけじゃないのです。それを目撃供述の問題点としてきちんと検事のほうで分かっていれば、まだちょっとは違ったんじゃないかと。起訴するかどうか、起訴しないとかいう事も有り得たと思うのです。だから、いわばそういう目撃供述の問題点とかしっかりと頭に入れる、そうした検事が検事になることによって初めて、そういう冤罪は直接的に防げる可能性が高いのじゃないかと思い、僕は検事になろうと思ったのです。
若 狭目撃供述っていうのは「いい加減」なんですよ。人間の供述って言うのは本当に「いい加減」なんですよ。そこから出発しないといけないです。逃げていく最中の後姿とか横顔をね、チラって見ただけで、その後「全部間違いない」って話しになるわけです。しかしそんなものってのはね、逃げる時には、要するに「強制わいせつをした犯人だ」と分かっていればもっとしっかり印象に残りますが、公園の中をバーって走っていく姿だけですから、「なんか用事があって走っているんだろう」っていうふうに思えば記憶にだってそんなに残るわけじゃないのです。それを目撃供述の問題点としてきちんと検事のほうで分かっていれば、まだちょっとは違ったんじゃないかと。起訴するかどうか、起訴しないとかいう事も有り得たと思うのです。だから、いわばそういう目撃供述の問題点とかしっかりと頭に入れる、そうした検事が検事になることによって初めて、そういう冤罪は直接的に防げる可能性が高いのじゃないかと思い、僕は検事になろうと思ったのです。
だから検事になってから、ずっとこの26年間は「冤罪」の問題を考えてきました。今に始まったことではなく、27、8年前のことが全部原点にあるんだと。だから、ライフワークとして人間の供述の問題点とか、人間の記憶には色とか時間とかいうものについて、どのような特徴があるのかなどを。人間の記憶のメカニズムなどを一応ライフワーク的に研究はしてきているのです。
冤罪事件の根本は「思い込み」
若 狭検事っていうのは、やっぱり検事も警察も裁判官もそうですけど、「被疑者・被告人っていうのはウソをつくもんだ」という習わされた意識があるのです。ここが問題なのですけど。つまり、「慣習」と言うか。なぜそういう習慣になってしまうのかと言うと、来る人来る人が最初はみんなウソつくわけです。「やっていない」と。ところがそのうち、「やりました」という話になるわけです。そういう事を何回も重ねていると、否認している人に対しても、「またこれもウソをついているのだろう」というような思い込みが生じてしまうのです。そこがそもそも冤罪事件の根本にあるのです。
これは良い例なのですが、修習生が初めて「取調べ」をするとですね、大体「被疑者が言っていることは本当だ。被疑者の言い分は本当ですね」というふうにみんな思ってしまうのです。ところが、そのうち調べていくと「ウソでしたって」被疑者が言うわけです。最初は、修習生はみんな被疑者にだまされてしまうのです。ある意味、そういう「だまされる」ということがあると、段々と「被告人・犯人・被疑者はウソをつくもんだ」という意識になって、「だまされちゃいけない」という意識が芽生えて来てしまうのです。
そこが一つの問題点なのですが、これは裁判官もそうなのです。裁判官もやっぱり否認している被告人を前にして裁判を、それこそもう何十回、何百回とやっているのです。そのうちに否認していても、「本当にやっていないから否認しているのか」。それとも「いつもと同じように否認しているだけなのか。否認のための否認なのか」ということの区別がつかなくなってしまうのです。見極めがつかなくなってしまうのです。
裁判員裁判には冤罪防止の効果がある
若 狭そこにすごい問題点があるのです。だからこそ、裁判員というのはそういう「慣れ」が無いわけですよね。初めてなのですから。だから、被告人の言っている言葉が、「やってない」という言葉を、出発点としておそらくそのまま受け取るわけです。そこが裁判員裁判で、裁判員、つまり一般市民が裁判に参加するところに非常に大きな冤罪防止の効果があると思っています。
弁護人もきちんとしたストーリーを用意して
若 狭今までの裁判では、検察官はある主張をしますよね。事実の主張を。ストーリーを主張するわけです。で、それがきちんと証明できているかどうかによって、無罪有罪って決めるっていうことになっているのですよね。まぁ、検察官に立証責任があるっていうことになっているのですが。でも裁判員裁判においてはですね、僕はそういう構図ではなくて、検察官の主張に対して、弁護人が「アナザーストーリー」と言って、もう一つのストーリーをきちんと用意する必要があるんだと思います。それは何故かと言うと、裁判員が「こっちの主張とこっちの主張。どっちが説得力があるか」という比較の上において、「こっちだ。あっちだ」と言って判断しやすくなる。それで、裁判員の適切な判断を求めるには、争点を浮き彫りにして、しかも、弁護人と検察官のストーリーをきちんとガチンコで、争点的にして、それで、裁判員はいわば審判官、ジャッジみたいな形ですね。まさしく「ジャッジ」なのですけれど。こっちが正しいとか、こっちの方が説得力があるか、とか。そういう形です。そういう設定をしてあげる方が非常に分かりやすいし、適切な判断が出来るのではないかと思います。これまでのような「検察官の主張はこうです」と。で、弁護人が検察官の主張の一部だけを「ここはおかしい」とかなんとか言ったところでは、それでは争点が浮き彫りにならない。裁判員とすると。じゃあ「どこが問題点なのか」というってことがよく分からなくなっちゃうんだと思う。で、そのためには、弁護人もきちんとしたストーリーを用意して、対立構造にした上で、裁判員に判断してもらう、というようにすることが大事だと思います。
インタビュアーなるほど。それは弁護士の弁護の方法も大きく変えていかないといけないってことですね。
若 狭だから、今までは、検察官に立証責任があるっていうのはその通りだし、「検察官の主張にちょっとでも腑に落ちないところがあったらそれは無罪ですよ」というのは、それは論理的にも、理念的にも、そうなのです。ただ、実際問題として、裁判員裁判においては、やっぱり弁護人の「この事件はこういう感じなんですよ。だから、したがって、これは犯人ではありませんよ」とかいうような形で、体系だった大きなストーリーをきちんと用意するという方が、場合によって説得力が出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。検察官の主張を一つ一つ、細切れで、「そこは違う」とか言うよりは、もっと体系的に「こうですよ」って。「だから犯人じゃありませんよ」と言う方が、説得力があるし、裁判員は少なくとも判断がしやすい。短時間の内に判断を求められるわけですから、そういう意味では、そういうふうな働きかけをしていくことになるんじゃないかなぁ、と思っています。
※敬称略
インタビュアー:坂上暢幸(裁判員ネット理事)
(第3部に続く)